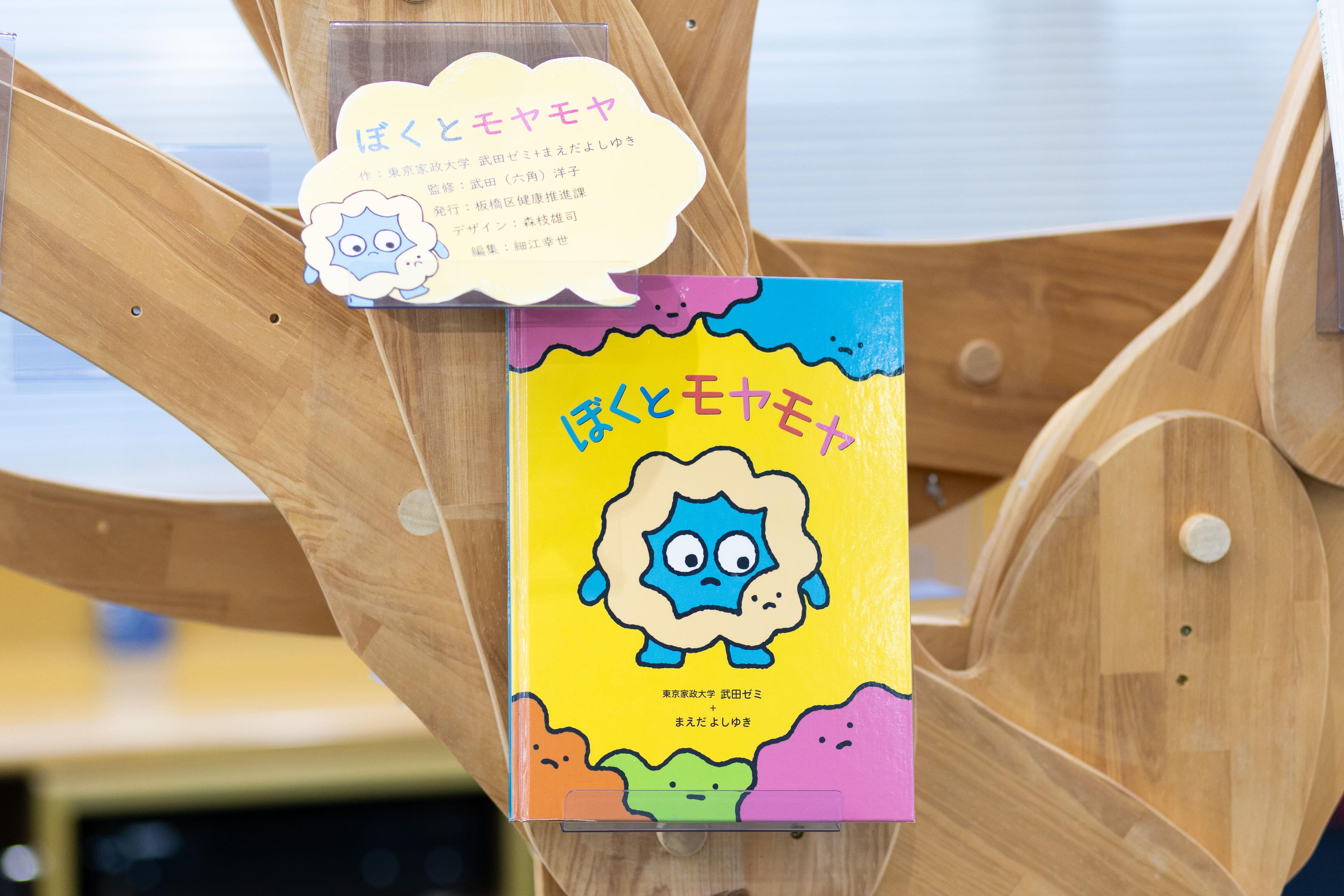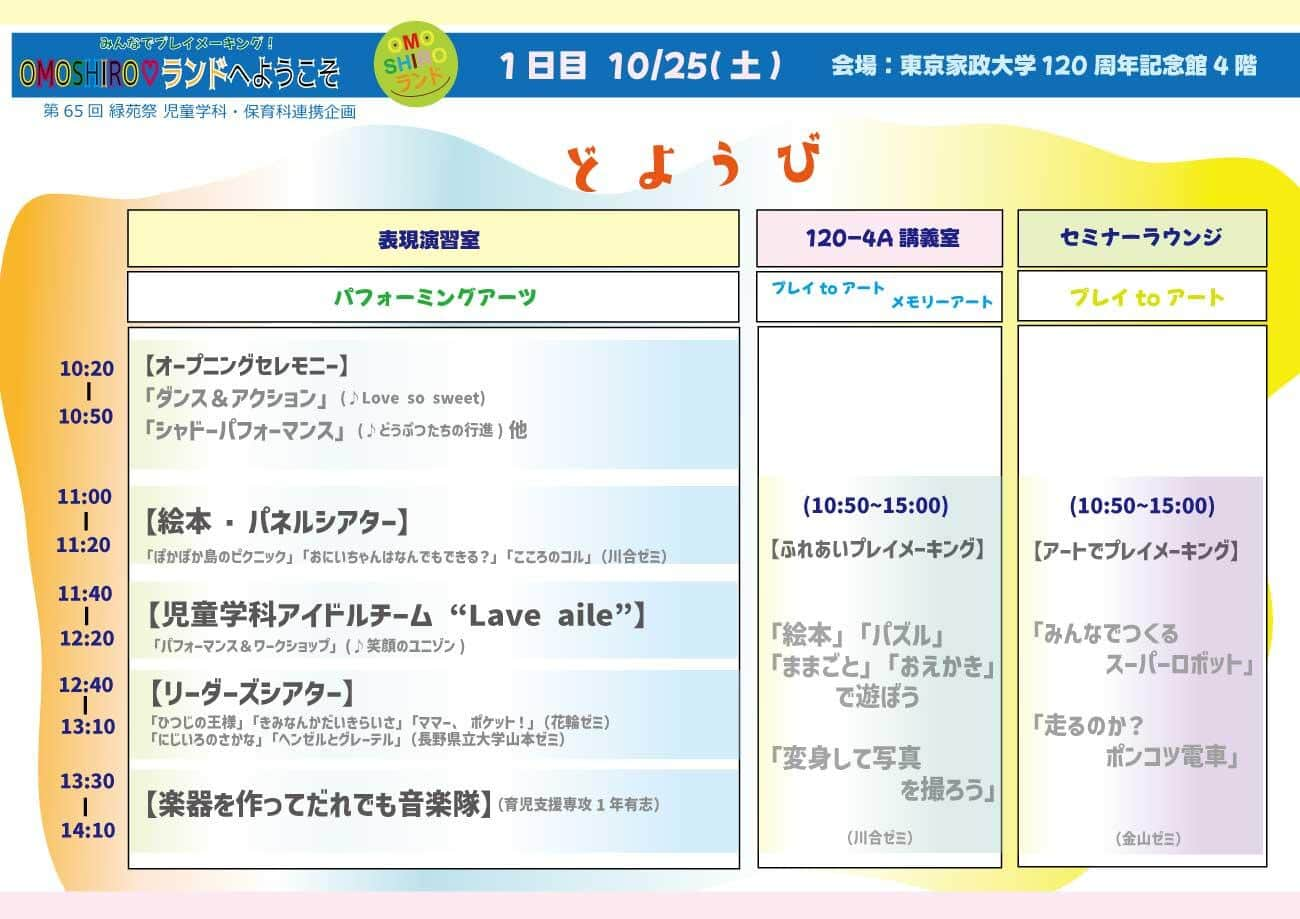TOPICS
学科の概要
カリキュラム・実習
専攻の特色・ポイント
児童学専攻
児童学専攻に設置された「子ども理解研究」「児童学特別演習A〜D」(「ミュージックパフォーマンス」「保育(遊び)環境デザイン」など)「児童学特別講義 A〜D」(「インクルーシブ保育」「子どもと文化」など)を通して、質の高い保育を学び、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格取得のための学修を高度なレベルで行います。
育児支援専攻
育児支援専攻に設置された「育児支援研究」「育児支援特別演習 A〜D」(「人をつなぐコミュニケーション技法」「病児のケアと親子のサポート」など)「育児支援特別講義 A〜D」(「世界の子育て支援」「保育カウンセリング」など)を通して、現代的なテーマを幅広く学び、幼稚園教諭一種免許状、保育士資格取得のための学修を高度なレベルで行います。
ゼミ・研究室紹介

児童学科のゼミは、3年次のゼミナールⅠや児童学研究法の学修をもとに、自らの興味・関心のあるテーマを定め、テーマに関係のある指導教員の指導と助言を得ながら、文献研究やフィールド調査・実験・制作などを行います。
また、その成果は、論文や作品という形で提出され、他のゼミや後輩などへの発表も行います。卒業研究に取り組むことで、絶えず変化する現代社会で生きていくうえでの、学び方の基礎を自らの力で構築することができるようになることを目的としています。
先輩の声
[児童学専攻]
[育児支援専攻]
資格・就職
-
児童学専攻
- 幼稚園教諭一種免許状 (全員取得が原則)
- 保育士資格 (全員取得が原則)
- 社会福祉主事任用資格
- 図書司書教諭
-
育児支援専攻
- 幼稚園教諭一種免許状 (全員取得が原則)
- 保育士資格 (全員取得が原則)
- 社会福祉主事任用資格
- 認定ベビーシッター資格
-
卒業生の就職先・活躍フィールド
- 保育士
- 幼稚園教諭
- 保育教諭
- 図書館司書
- ベビーシッター
- 児童指導員 など
※専攻によって異なる場合がございます。

動画一覧
教員一覧
-
教授
岩崎 美智子
Michiko Iwasaki
担当科目
子ども家庭福祉、社会的養護Ⅰなど -
教授
榎沢 良彦
Yoshihiko Enosawa
担当科目
保育原理、子ども理解と援助、基礎ゼミナール -
教授
榎本 眞実
Mami Enomoto
担当科目
カリキュラム論、保育内容演習(人間関係)、幼児と人間関係、教育実習事前事後指導、教職実践演習(幼) -
教授
尾崎 司
Tsukasa Ozaki
担当科目
保育実習指導I・II・III、保育実習I・II・IIIなど -
教授
金山 和彦
Kazuhiko Kanayama
担当科目
「幼児と表現」「保育内容 表現の指導法」「保育内容演習(表現)」「保育の理解と方法C(造形)」「保育の造形実技A・B」 -
教授
金城 悟
Satoshi Kinjo
担当科目
社会福祉概論、社会福祉、保育内容演習、保育実習Ⅰ、保育実習指導Ⅰ、基礎ゼミナールなど -
特任教授
黒谷 万美子
Mamiko Kurotani
担当科目
子どもの保健、子どもの栄養など -
教授
是澤 優子
Yuko Koresawa
担当科目
児童文化、保育内容の理解と方法D(言葉)、児童学総論など -
教授
笹井 邦彦
Kunihiko Sasai
担当科目
音楽?I、幼児音楽B、保育内容の研究(表現II)、保育総合表現、総合演習 -
教授
笹井 邦彦
Kunihiko Sasai
担当科目
幼児音楽B、保育内容の研究(表現II)、保育総合表現、総合演習 -
教授
佐藤 康富
Yasutomi Sato
担当科目
幼児と環境、保育内容演習(環境)、保育内容の指導法(環境)、生活 -
教授
鈴木 隆
Takashi Suzuki
担当科目
保育内容演習(健康)、保育内容の理解と方法A(体育)、幼児と健康、からだとスポーツ、体育と健康、自校初年度教育科目 -
教授
武田 洋子
Yoko Takeda
担当科目
子ども家庭支援論、教育相談、在宅保育、子育て支援、保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱなど -
教授
戸田 雅美
Masami Toda
担当科目
保育者論 保育(遊び)指導論 児童学研究法、児童学総論、幼児と言葉など -
教授
西海 聡子
Satoko Nishikai
担当科目
子どもの歌と伴奏、保育内容の理解と方法B(音楽)、保育内容の研究(表現B)、他 -
教授
花輪 充
Mitsuru Hanawa
担当科目
保育内容の研究(表現II)、保育内容演習(表現)、幼児と表現、保育総合表現、演劇表現、基礎ゼミナール -
教授
平山 祐一郎
Yuichiro Hirayama
担当科目
児童学総論、基礎ゼミナール、教育心理学、保育心理学、育児支援特別演習、ゼミナールⅠ・Ⅱなど -
教授
堀 科
Shina Hori
担当科目
乳児保育演習、保育方法論、育児支援特別演習C -
教授
渡部 晃正
Terumasa Watanabe
担当科目
教育原論、教育・保育制度論、ゼミナール、他 -
准教授
荒井 庸子
Yoko Arai
担当科目
障がい児保育演習、特別支援教育概論、教職・保育実践演習、教育実習(幼)など -
准教授
石川 昌紀
Masanori Ishikawa
担当科目
障がい児保育演習、特別支援教育概論、教職・保育実践演習、教育実習(幼)ほか -
准教授
鵜殿 篤
Atsushi Udono
担当科目
教育概論、保育方法論(ICT) -
准教授
梅谷 千代子
Chiyoko Umetani
担当科目
からだとスポーツ I・II、体育、幼児体育 -
准教授
柿沼 芳枝
Yoshie Kakinuma
担当科目
教育実習(幼)、教職実践演習、子どものことばと文化、保育内容演習(ことば)など -
准教授
佐藤 隆弘
Takahiro Sato
担当科目
教育心理学、子ども家庭支援の心理学、基礎ゼミナールなど -
准教授
平野 順子
Junko Hirano
担当科目
子ども家庭支援論、子ども家庭支援の心理学、キャリアデザイン、生活経営学、他 -
准教授
前田 和代
Kazuyo Maeda
担当科目
保育内容総論、カリキュラム論、教育実習(幼)、教職実践演習、自校実習など -
准教授
松本 なるみ
Narumi Matsumoto
担当科目
社会的養護Ⅰ、社会的養護Ⅱ、保育実習Ⅰ、基礎ゼミナールなど -
准教授
梁川 悦美
Etsumi Yanagawa
担当科目
保育内容の理解と方法A(体育)、幼児と健康、保育内容健康「健康」の指導法、幼児体育など -
講師
木村 美佳
Mika Kimura
担当科目
子どもの保健 子どもの健康と安全 幼児と健康 実習指導 ゼミナールⅠ.II 児童学総論 育児支援特別演習D -
特任講師
齊藤 紀子
Noriko Saito
担当科目
音楽表現、子どもの歌と伴奏、幼児と表現、保育内容の理解と方法B(音楽)、人間と学びD(こどもと芸術をめぐって)、基礎ゼミナール、ゼミナールⅠ・Ⅱ、卒業研究 -
講師
鈴木 彬子
Akiko Suzuki
担当科目
保育者論、子育て支援、教職・保育実践演習、保育実習指導Ⅰ・Ⅱなど -
特任准教授
山本 秀子
Hideko Yamamoto
担当科目
保育者論、教育実習、教育実習事前事後指導、教職実践演習、児童学特別演習 -
特任講師
大西 明実
Akemi Onishi
担当科目
保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、保育実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、乳児保育Ⅰ -
特任講師
川合 沙弥香
Sayaka Kawai
担当科目
保育内容の理解と方法C(造形)、造形表現、保育内容演習(表現)、幼児と表現、保育実践実技Bなど -
特任講師
高畑 祐子
Yuko Takahata
担当科目
保育実習指導Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 保育実習Ⅰ、Ⅲ -
助教
大久保 麻彩
Maaya Ohkubo
担当科目
なし -
助教
金子 日菜乃
Hinano Kaneko
担当科目
なし -
助教
鈴木 春彦
Haruhiko Suzuki
担当科目
なし -
助教
新妻 千紘
Chihiro Niizuma
担当科目
なし
学科紹介UNDERGRADUATE
-
共創デザイン学部
※2026年4月〜(仮称・構想中) -
栄養学部
-
児童学部
-
人文学部
-
健康科学部
-
子ども支援学部